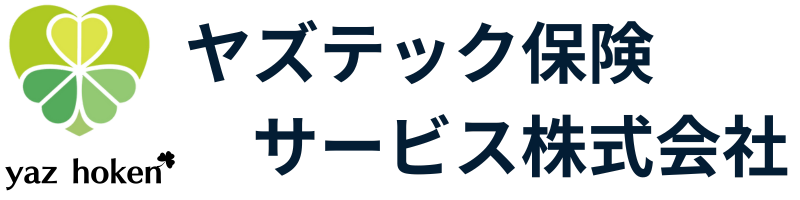はじめに
高齢化が進む一方で、親世代と同居する共働き家庭も多く、「自分や家族の将来の介護に備えたい」という声が年々増えています。
古河市の高齢化率は約30%を超え、今後も上昇傾向
親の介護や自分の老後に対する不安を感じる50代〜60代の相談が急増
介護費用の平均は全国で月額約8〜12万円。自己負担が重くなりがち
公的介護保険だけではカバーしきれない実費負担を補うため、
民間の「個人向け介護保険」の必要性が高まっています。
今回の記事では、個人向けの介護保険について詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 個人向け介護保険とは
- 個人向け介護保険のメリット
- 個人向け介護保険のデメリット
- 公的介護保険と個人向け介護保険の違い
- 個人向け介護保険の3つのタイプ
- 各商品の特長、おすすめポイント、おすすめする人
- よくある質問
個人介護保険とは?
個人向け介護保険とは、将来、介護が必要になったときの経済的な負担をカバーするための民間保険です。
公的な介護保険制度(40歳以上が加入する介護保険制度)とは別に、自分自身で任意に加入するもので、介護状態に認定された際に一時金や年金形式で保険金が受け取れるのが特徴です。
最近では、要介護状態になる確率の上昇や、家族の介護負担への懸念から、「自分で備える介護保険」のニーズが高まっています。
介護にかかる費用の目安
全国平均で、介護期間は約4年半、総費用は約500万円〜700万円と言われています。
特に古河市では自宅介護を選ぶ家庭が多く、住宅リフォーム・介護用品・介護サービス利用など、想定以上の費用がかかるケースが目立ちます。
加入のベストタイミング
40代後半〜50代前半:保険料がまだ安く、将来の介護リスクに備える絶好のタイミング
60代以上:健康状態に応じた加入条件を相談しながら、必要な保障だけを確保
当代理店では、年齢や家族構成に合わせて最適な加入時期をご案内しています。
個人向け介護保険のメリット
公的介護保険ではカバーしきれない費用を補える
公的介護保険は基本的な介護サービスを受けるための支援制度ですが、自己負担は原則1〜3割あり、さらに住宅改修や介護用品の購入費、在宅介護の人件費などは対象外となる場合も多くあります。
個人向け介護保険に加入しておくことで、これらの実費負担を補う資金を確保でき、「介護費用のために貯金を切り崩す」といった不安を軽減できます。
介護状態に応じた柔軟な給付形態
民間の介護保険は、保険会社によって一時金タイプ・年金タイプ・併用タイプなど給付形態を選べるのが強みです。
例えば、初期費用に充てるための一時金を受け取り、その後の継続費用を年金形式で受け取るプランなど、ライフスタイルや家族構成に合わせて設計できます。
また、認知症など特定疾病にも対応する商品もあり、幅広い介護リスクに備えられます。
保険料が一定で将来の負担が予測しやすい
多くの介護保険は契約時に保険料が固定されるため、物価上昇や制度改正の影響を受けません。
特に一時払いタイプであれば、将来の支払い負担がゼロになるため、老後資金計画の安定化にも役立ちます。
家族への精神的・経済的負担を軽減できる
介護は、家族にとっても時間・費用・労力の大きな負担となります。
介護保険の給付金があることで、介護サービスの選択肢が広がり、家族の負担を軽くできる点も大きなメリットです。
「介護離職」や「介護疲れ」を防ぎ、本人・家族双方がより良い生活を維持しやすくなります。
個人向け介護保険のデメリット
保険料負担がある(掛け捨て型は特に注意)
介護保険は「備え」のための保険なので、介護状態にならなければ保険金を受け取れない掛け捨て型もあります。
「支払った分がムダになってしまう」と感じる方もいます。
一方で、最近では「死亡保障」や「返戻金」が付いた商品もあるため、貯蓄性と保障性のバランスを見ながら選ぶことが重要です。
介護認定の基準が保険会社によって異なる
保険会社ごとに「要介護状態」とみなす基準が異なります。
例えば、公的介護保険の要介護2以上で給付されるタイプもあれば、自社独自の基準(身体動作や認知症の度合い)を用いるタイプもあります。
加入前に「どのような状態で給付されるか」を必ず確認しておく必要があります。
加入時の健康状態で制限がある
民間の介護保険は、告知書や健康診断の結果によって加入を制限される場合があります。
持病がある場合や、高齢での加入希望の場合は、引受基準緩和型の商品を選ぶとよいでしょう。
インフレリスク・金利変動リスク
長期間の契約となるため、将来的に介護費用や物価が上昇した場合、
契約時の給付金額では実際の介護費用を賄いきれない可能性もあります。
一時払い・終身タイプを選ぶ際には、資産全体のバランスも考慮することが大切です。
公的介護保険と個人向け介護保険の違い
多くの方が誤解しやすいのが、「公的介護保険」と「民間の介護保険(個人向け)」の違いです。
| 項目 | 公的介護保険 | 民間の介護保険(個人向け) |
|---|---|---|
| 対象 | 40歳以上 | 年齢・健康状態による加入可 |
| 保険料 | 所得に応じて徴収 | 自由に設計可能 |
| 給付内容 | 介護サービス費の一部補助 | 現金給付・一時金・年金型など自由 |
| 保障範囲 | 公的基準による | 自分で選択(介護度・支払回数など) |
| 目的 | 最低限の生活保障 | 介護生活の質を高める・家族負担を軽減 |
つまり、民間の介護保険は「自分の希望する介護を叶えるための備え」として位置づけられます。
個人向け介護保険の3つのタイプ
民間の介護保険には大きく分けて3つのタイプがあります。
一時金タイプ
介護状態になった際に、まとまった金額が一括で支払われるタイプ。
住宅のバリアフリー改修や介護ベッド購入などに活用できます。
年金タイプ
介護が必要になったとき、毎月または毎年、年金のように給付金を受け取れるタイプ。
長期的な介護費用の補填に適しています。
一生保障タイプ(終身型)
要介護状態がいつ発生しても、一生涯保障が続くタイプ。
認知症や老衰など、晩年期のリスクにも安心して備えられます。
各社主要商品の特長とおすすめポイント

SOMPOひまわり生命
商品名:家族がつながる介護保険
詳細
SOMPOひまわり生命が提供するこの保険は、通信販売プラン(オンライン・郵送など)を通じて加入でき、終身保障タイプで、保障と予防をセットにした設計となっています。
認知症・骨折の保障が基本契約に含まれる、介護保障オプション(特約)によって「介護一時金」「介護年金」が設定可能である、保険期間・払込期間は終身型、主契約・特約ともに解約返戻金がない等の特徴があります。
おすすめポイント
- 認知症保障・骨折保障など、最近ニーズが高いリスクをカバーできるオプションを持つ
- 保険の柔軟性が比較的高めで、給付方式(年金/一時金)を選べる構成
- ブランドがSOMPOグループで安心感があり、他のSOMPO系保険と統合しやすい
おすすめする人
認知症リスク・骨折リスクを特に重視したい人
保障方式を選びたい人(年金型・一時金型など)
他の生命保険・医療保険とまとめてSOMPO系で揃えたい人
アクサ生命
商品名:ユニット・リンク介護プラス
詳細
アクサ生命の「ユニット・リンク介護プラス」は、資産形成と介護・死亡保障を両立させる変額保険です。
特に「人生100年時代」に備え、長期的な視点での資産形成を希望する方に適しています。
■一生涯の介護・死亡・高度障害保障
要介護2以上や認知症の状態に至った場合でも、介護・死亡・高度障害保険金が支払われます。これにより、万一の事態にも安心して備えることができます。
■資産形成と保障の二段構造
第1保険期間中に積立金を形成し、その後、第2保険期間に移行することで、終身の保障を確保します。この仕組みにより、退職後の生活資金や長期的な介護リスクに備えることが可能です。
■多彩な運用選択肢
10種類の特別勘定(ファンド)から選択し、運用割合を自由に設定できます。これにより、リスク許容度や投資目的に応じた資産運用が可能となります。
■保険料払込免除特約の活用
3大疾病や7大疾病に罹患した場合、以後の保険料の払込が免除される特約を付加できます。これにより、病気による経済的負担を軽減できます。
おすすめポイント
資産形成と保障を同時に実現したい方。
長期的な視点での資産運用を希望する方。
万一の事態に備え、介護・死亡・高度障害保障を確保したい方。
疾病による保険料の負担を軽減したい方。
おすすめする人
中長期的な資産形成を考えているが、保障も重視したい方。
公的な介護保険だけでは不安な方。
疾病による保険料の負担を避けたい方。
資産運用に関心があり、リスクを適切に管理できる方。
マニュライフ生命
商品名:パワー・カレンシー(介護保障タイプ)
詳細
マニュライフ生命の「パワー・カレンシー(介護保障タイプ)」は、主に次のような特徴があります。
外貨建て・契約通貨を選択できる仕組みを備えている
たとえば米ドルあるいは豪ドルなどの契約通貨を選択し、積立・運用を行ったうえで介護年金や年金として受取ることが可能です。
「終身」や長期にわたって介護年金を受け取れるプランがある
「終身」あるいは長期にわたって介護年金を受け取れるプランが用意されており、公的介護保険制度において要介護2以上と認定された場合には「一生涯にわたる介護年金支払」が開始される据置プランなどが用意されています。
介護年金支払の総額の最低保証の仕組みがある
介護年金支払の総額が「契約時に原資として定められた金額の100%または110%」を最低保証するという仕組みが用意されており、契約時点で保証割合を選択できるようになっています。
運用面に配慮がある
積立利率・運用利率の設定や積立通貨など、運用面に配慮がある仕組みとなっており、市場金利・為替動向の影響を受けることが明記されています。
契約時に健康状態の告知不要、または告知が比較的緩やかなタイプ(商品によって異なります)であるという情報もみられます。
おすすめポイント
長期にわたる介護リスクへの備え
要介護2以上と認定された場合に一生涯の介護年金支払が開始されるプランがあるため、晩年における介護費用・介護生活の経済的な不安を軽減できます。運用・資産形成との併用が可能
外貨建て・運用型の商品設計により、「介護保障」だけでなく「資産を長期的に育てる」視点も持ちたい方にメリットがあります。保障内容の最低保証付き
契約時の原資に対して100%または110%の保証が付いており、「払った金額から著しく下回る可能性を抑える」設計になっている点が安心材料となります。通貨選択・柔軟な設計
契約通貨を選べたり、プラン(据置・即時払)を選択できたりすることで、ライフステージ・資産状況・為替リスクを考慮した設計が可能です。介護認定前後で使い方が変えられる
介護認定されなかった場合には年金として受取開始、認定された場合には介護年金として受取開始というような二つのフェーズに対応できます。これは「介護が必要な状態にならなかったら資産として使う」「なったら保障として使う」という視点に立っています。
おすすめする人
将来の介護リスク(要介護2以上になる可能性)を真剣に考えており、長期的に介護保障を確保したい方。
老後の資産形成も視野に入れており、資産運用や外貨活用にも興味を持ち、ただ保障だけではなく運用効果も期待したい方。
ある程度まとまった資金を用意できる、あるいは資産運用を含めた保障設計を行いたい中高年層(たとえば50代前後~)で、将来的に介護が必要になったときの「安心材料」を欲している方。
通貨分散や資産分散にも関心がある方で、円建だけでなく外貨建て商品のメリット・デメリットを理解しながら加入できる方。
自営業・資産家・企業退職者など、保障と運用を両立させた「次のステージ」のライフプランを考えている方。

アドバイザー 齊藤
保険代理店として表彰歴がある保険コンサルタント
👉ワンポイント説明
長生きのリスク「介護」は他人事ではなく「自分事」として考えたほうが良いでしょう。早いうちから介護と認知症、高まるリスクに備えることが望まれます。
よくある質問
公的介護保険と民間の介護保険はどう違うのですか?
公的介護保険(介護保険法に基づく制度)は、40歳以上の全国民が加入する「社会保険制度」で、要介護認定を受けた際に介護サービス費用の一部(通常1〜3割)を自己負担し、残りを国が負担する仕組みです。
一方、民間の介護保険は、介護が必要になったときに現金で保険金や年金が受け取れる「生活支援・経済補填型の保険」です。
公的制度ではまかなえない「介護施設の差額費用」「在宅介護の人件費」「家族の休業補償」などに充てられます。
介護状態のどの段階で保険金が支払われるのですか?
保険会社によって異なりますが、多くの個人向け介護保険では「公的介護保険制度における要介護2以上」が支払基準になっています。
一方で、より軽度な「要支援」「要介護1」から支払対象とする商品もあります。
また、保険会社独自の「所定の要介護状態」や「認知症による介護状態」などを基準とするタイプもあります。
保険金はどのように受け取れますか?
受け取り方法は大きく分けて2種類あります。
一時金タイプ:介護が必要になった時点でまとまった金額を受け取れる
→ 介護設備の購入・住まいのリフォームなどに使いやすい
年金タイプ:一定期間または一生涯、毎月介護年金を受け取る
→ 継続的な介護費用の補填に向く
多くの保険では、どちらか一方、または両方を選べる設計になっています。
介護状態にならなかった場合はどうなりますか?
商品によって異なります。一般的には以下の3タイプがあります。
掛け捨て型:介護状態にならなければ保険金は支払われませんが、保険料が安い。
貯蓄型(返戻金あり):介護にならなかった場合でも、死亡時や解約時に返戻金や死亡保険金を受け取れる。
一時払い終身型:介護にならなくても、一定期間後に「年金」として受取可能。
どのくらいの保険金額にすればいいですか?
介護の自己負担費用は、在宅・施設で大きく変わります。
平均的には以下のとおりです。
| 介護の種類 | 自己負担費用(平均) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 在宅介護 | 約7〜10万円/月 | 4〜5年 |
| 施設介護 | 約12〜18万円/月 | 3〜5年 |
したがって、一時金100〜300万円+月5〜10万円の年金タイプを選ぶ方が多いです。
家族構成や貯蓄状況に応じて「不足分を補う」形が現実的です。
加入できる年齢に制限はありますか?
一般的には40歳〜75歳くらいまでが加入対象です。
ただし、SOMPOひまわりやアクサ生命などでは、80歳まで加入できるプランもあります。
マニュライフ生命などの「一時払いタイプ」は、60代〜70代の加入が最も多く、
「退職金や預貯金を老後の介護資金に転換」する目的で利用されています。
保険料の払い方にはどんな方法がありますか?
主に以下の3つのタイプがあります。
月払い・年払い:現役世代に多い。コツコツ積み立てながら保障を継続。
一時払い:まとまった資金(退職金・貯蓄など)を元手に、一度で払い終えるタイプ。
短期払い(5年・10年など):現役中に払い終え、老後は負担をなくす設計。
認知症が原因の介護でも保険金は出ますか?
はい。多くの保険会社では「認知症による要介護状態」も支払対象に含まれます。
さらに、認知症特約を付けると「軽度認知症(MCI)」や「要支援1〜2」でも支払対象となる場合があります。
持病があっても加入できますか?
保険会社・商品によりますが、
「持病があっても加入できる」引受緩和型や告知簡易型も増えています。
高血圧・糖尿病など、軽度でコントロールされていれば加入可能なケースもあり。
告知内容が「過去2年以内に入院・手術の有無のみ」など簡略化された商品も。
ただし、一般の保険に比べて保険料はやや高く設定されます。
加入するタイミングはいつがベストですか?
最も理想的なのは「40代後半〜50代前半」です。
この時期はまだ健康状態が良く、保険料が比較的安く済みます。
60代以降になると加入制限や保険料上昇のリスクが高まるため、「健康であるうちに準備する」ことが大切です。

アドバイザー 齊藤
保険代理店として表彰歴がある
保険コンサルタント
👉ワンポイント説明
介護が必要になった原因のトップは、認知症です。(約20%)
認知症保障に特化した保険商品に加入することをおすすめします。
まとめ
介護は突然やってきます。
公的保険だけでは十分に備えきれない時代だからこそ、「個人向けの介護保険」で早めの対策をおすすめします。
古河市で地域密着型の当代理店では、SOMPOひまわり・アクサ生命などの豊富なラインナップから、あなたとご家族の将来を守る最適な介護保険を選びます。